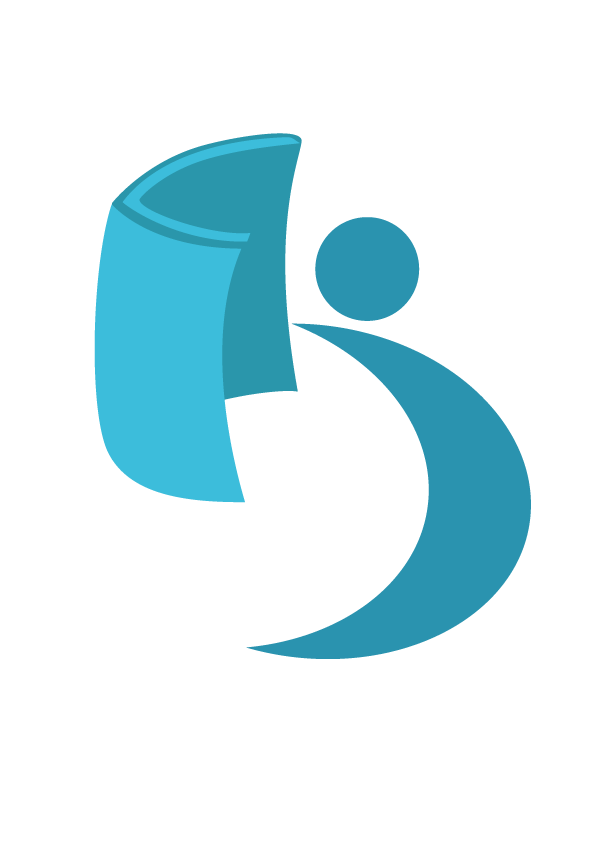資格試験の勉強を続けていると、必ずと言っていいほど訪れる壁があります。
それが「スランプ」です。
以前は解けていた問題が急に解けなくなり、知識も頭に入ってこない。
努力しているのに成果が見えず、自己否定が頭を支配する。
まさに悪循環です。
私自身も、そんなスランプに苦しんだ一人です。
しかし、この経験を通じて、スランプには明確なメカニズムがあることを知りました。
まず、スランプは脳の「過負荷状態」によって引き起こされることが多いと言われています。
長時間の集中やインプットのし過ぎにより、脳のワーキングメモリが疲弊し、新しい情報の処理や記憶の統合がうまくいかなくなります。
つまり、頑張れば頑張るほど、逆に思考が鈍ってしまうのです。
また、「できない自分」へのストレスが脳の扁桃体を刺激し、不安や焦りを増幅させます。
この状態が続くと、思考力や判断力を司る前頭前野の働きが低下し、さらに学習効率が下がるという負のスパイラルに陥ります。
では、どうすればこの状態から抜け出せるのでしょうか。
私が効果を感じたのは、「勉強方法の切り替え」です。
今までルーティーンのようにやっていたやり方を変え、「自分ができる部分」や「理解しやすいこと」からやり直してみました。
このやり方に変えたことにより、不思議なことに再び問題が解けるようになってきました。
これは、「自分の得意な分野で頭を悩ませすぎない」「できることにより自信を取り戻すこと」で記憶の定着が進んだ結果と考えられます。
つまり、スランプは「努力不足」ではなく、「処理過多」によるものや「自分へのストレス」であるとわかりました。
スランプは苦しいものですが、それは学びのプロセスが深まっている証でもあります。
もし今、行き詰まりを感じているなら、自分を責める前に、少し立ち止まってみてください。
それが次のステップへの大きな力になるかもしれません。