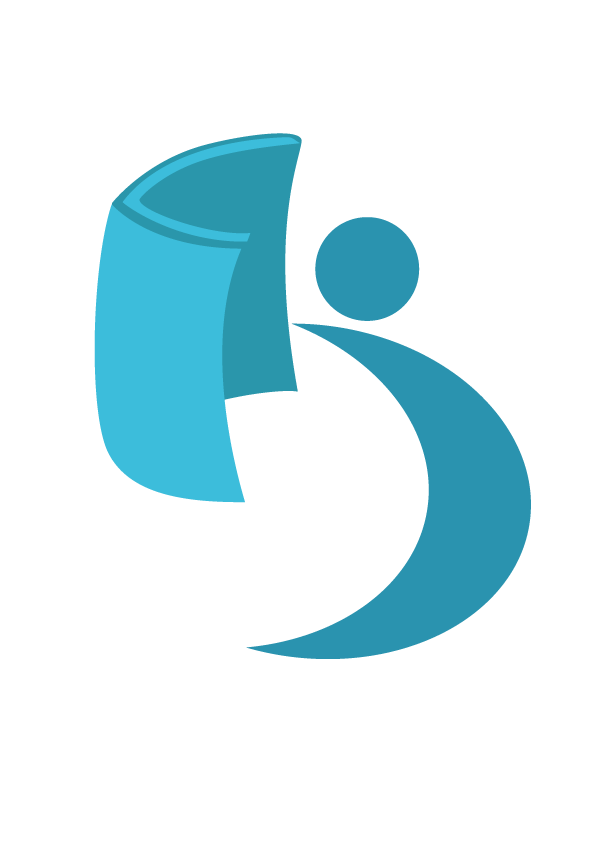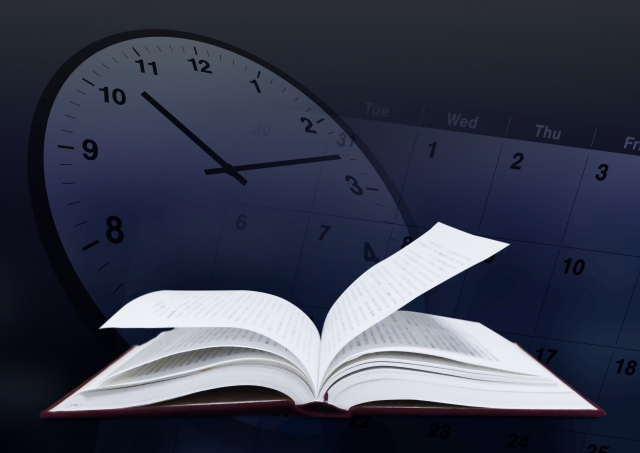速読という言葉には、「早く読めるようになりたい」という憧れが込められています。
多くの情報を短時間で処理できれば、勉強も仕事も効率が上がるように思えるからです。
しかし、「速く読んだ内容は本当に記憶に残るのか?」という疑問は、多くの人が感じるところではないでしょうか。
結論からいえば、速読と記憶の定着は相反する面を持ちつつも、目的と方法を誤らなければ両立することも可能です。
速読が有効な場面は、ざっと全体を把握したいときや、すでに知っている情報の再確認など、理解よりも「情報の収集や選別」が主な目的の場合です。
これは記憶に刻むというより、必要な情報をすくい取る作業に近いと言えます。
例えば新聞記事やレポートの要点を掴むには速読は有効ですが、資格試験のように細かな知識や用語を記憶する必要がある場面では、速読だけでは不十分です。
記憶に定着させるには、ある程度の「そしゃく時間」が必要です。
ゆっくり読んだ方が、意味を深く理解し、自分の知識と結び付けて覚えやすくなります。
また、音読やメモ、図解など、視覚や聴覚を活用する方法と組み合わせることで、記憶の定着率は大きく向上します。
つまり、情報の受け取り方を工夫しながら、時間をかけて理解していくプロセスが欠かせないのです。
ただし、速読がまったく役に立たないということではありません。
むしろ、全体像を素早く掴んだあとに、重要な部分をゆっくり精読するという「使い分け」が効果的です。
学習の初期段階で全体の構造を速読で把握し、その後に重要項目や苦手分野を重点的に読み込むことで、理解と記憶の効率は格段に上がります。
結局のところ、速読はあくまで手段であり、目的に合わせて使いこなすことが大切です。
記憶を定着させるためには、速さだけでなく、深さや繰り返しも必要です。
速読で学びを広げ、精読で理解を深める。このバランスを意識することで、学習効果を高めることができるでしょう。