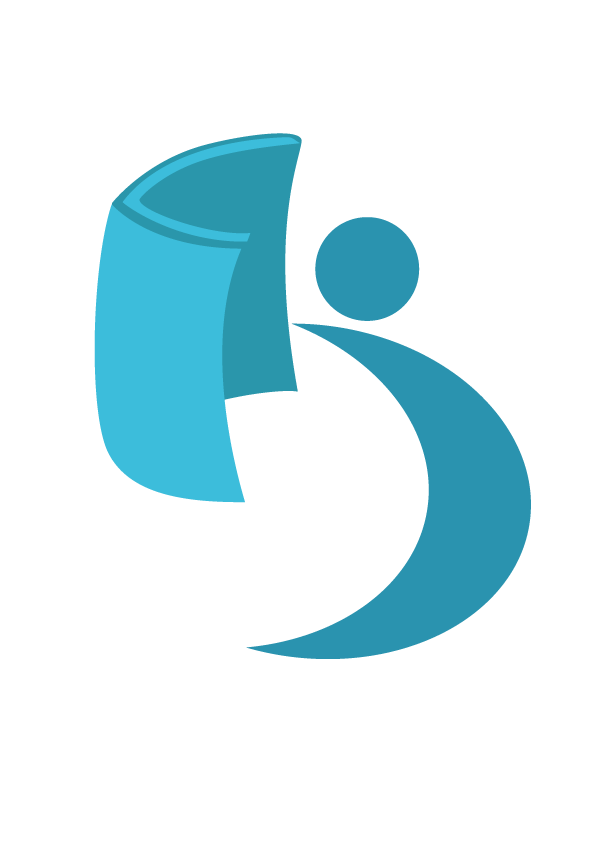前々回に引き続き、過去問題集の解き方の話をします。
資格試験対策において過去問題の活用は欠かせません。
しかし、いざ取り組む際に、
「古い年度から順番に解くべきか」
「最新の問題から解くべきか」
で迷う方は多いでしょう。
この選択が学習効率を大きく左右します。
古い年度の過去問から解くメリットは、出題の基礎的な部分を押さえられることです。
試験問題は年を追うごとに少しずつ傾向が変わりますが、基礎となる分野や考え方は大きくは変わりません。
特に古い問題には典型的な出題パターンが多く含まれており、基本理解を固めるには適しています。
一方で、情報技術の進化は早く、古すぎる問題には現在の試験範囲と合わないものや、実務にそぐわない知識も混ざっています。
そのため、本番に直結しない学習に時間をかけすぎるリスクもあります。
一方、新しい年度の過去問から解く場合の利点は、最新の出題傾向を早期に把握できることです。
社会や業界等のトレンドが色濃く反映されるため、直近数年分を解くことで「今、問われやすいテーマ」が見えてきます。
効率よく対策できる一方で、基礎が不十分な受験者にとっては難しく感じ、モチベーションを下げてしまう可能性もあります。
以上を踏まえると、最も効果的なのは「新しい年度から着手し、その後に過去数年分へ広げていく」という方法です。
まず最新1~2回分を解いて、どのような問題が出るのかを体感し、自分の得意・不得意を把握します。
その上で、弱点分野を補うために過去3~5年分の問題を解くと、反復演習となり知識が定着します。
10年以上前の問題は原則不要と思われますが、基礎確認や演習量を増やす目的で一部利用するのは有効です。
つまり、過去問演習は「古いか新しいか」の二者択一ではなく、学習段階に応じて組み合わせるのが最適です。
最初に最新年度で傾向をつかみ、その後に少し古い問題で知識を固める。この流れを意識することで、効率的に実力を伸ばすことができるでしょう。