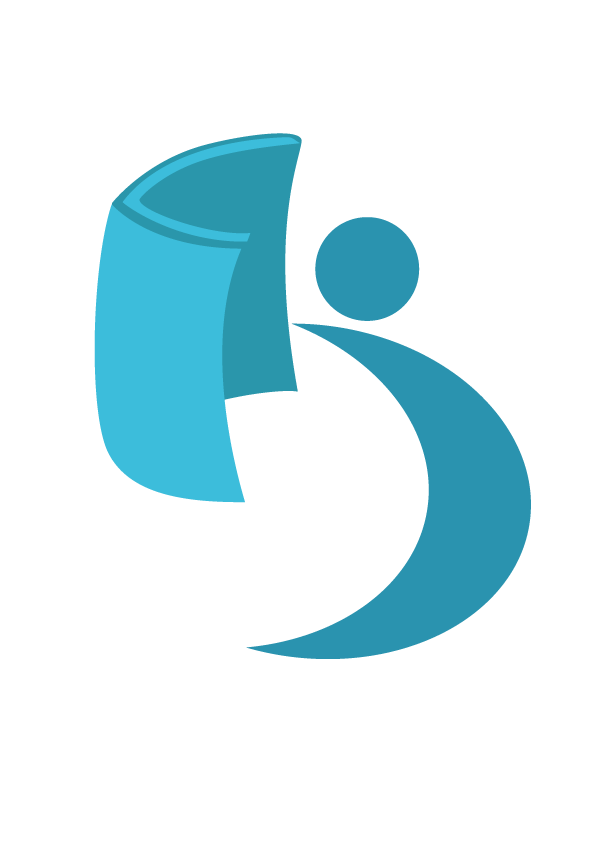社会人になると、多くの人が学ぶ時間を持たなくなると言われます。
学生の頃は、学ぶことが生活の中心にあり、授業や試験という仕組みが強制的に学びを促してくれます。
しかし、社会に出た途端、その仕組みはなくなり、学ぶかどうかは自分の意思次第になります。
だからこそ、学び続ける人は少数派となり、逆に学びを止めてしまう人が多数派になるのです。
私自身、「学ぶことこそ成長の源」だと考え、資格取得や読書、研修などを通して学びを続けています。
その姿勢に対して、「社会人なのに、よくそんなに勉強できますね」と感心されることがよくあります。
しかし、私は不思議に思います。
なぜ多くの人は学ばなくなってしまうのか。
学べば自分の可能性が広がり、仕事の成果が高まり、生き方の選択肢も増えると感じています。
その理由はいくつか考えられます。
第一に、「時間がない」という意識です。
仕事に追われ、家事や育児に追われ、気づけば一日が終わっている。
確かに時間的制約はありますが、本当の問題は「学ぶための時間を意識的に確保する」という習慣がないことにあります。
時間は与えられるものではなく作るもの。
この意識があるかどうかで、学びの継続に大きな差が生まれます。
第二に、「必要性を感じない」という点です。
現状の仕事に慣れ、評価もそこそこ安定してくると、人は変化を求めなくなります。
学ばなくても、今の生活は維持できる。
そのため、学びの優先順位が下がってしまうのです。
しかし、社会や技術が急速に変化する中で、現状維持は実は衰退につながることに気づかないまま、学ぶ習慣を手放してしまう人が多くいます。
第三に、「学び方がわからない」という問題があります。
学生時代は教科書もカリキュラムも用意されていましたが、社会人の学びは自分でテーマも方法も選ばなければいけません。これが意外に難しく、「何から始めていいかわからない」状態のまま、結局何もしないというケースが少なくありません。
では、どうすれば学び続ける人になれるのでしょうか。
答えはシンプルです。「小さく始めて、続けること」。
1日10分の読書でも、週に1つのニュースを深掘りするでも、何かを学ぶ習慣を積み上げることが、自分を成長させる力になります。
学びは一部の意識の高い人だけが行うものではなく、誰でもできる小さな行動の積み重ねなのです。
学び続けることは、自分の可能性を広げる最高の自己投資です。
社会人だからこそ、学びを止めず、自分の人生を主体的に育てていく姿勢が問われています。
学ぶ人が少ない社会だからこそ、学び続けるあなたの価値は、これからますます高まっていくはずです。