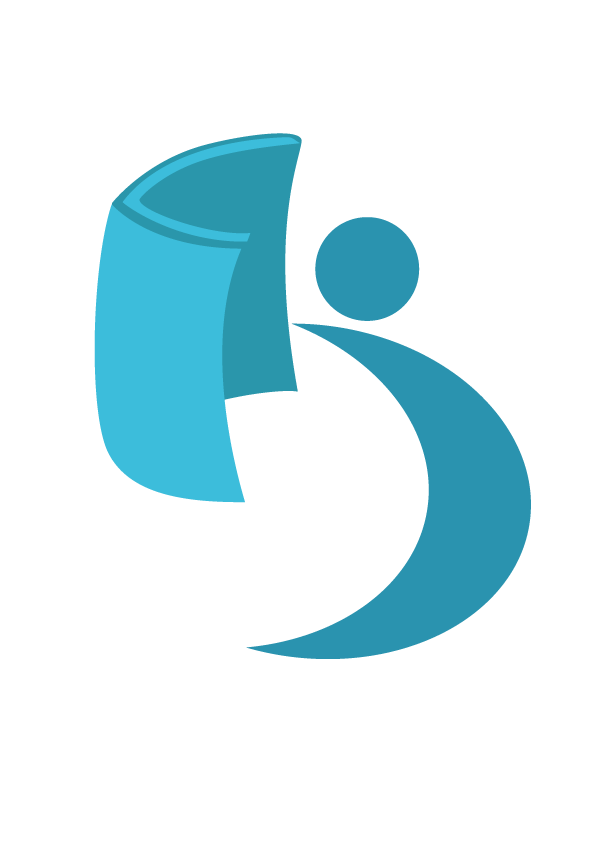普段、当たり前に使っている日本語。
英語は学生時代に何年も学んだのに、ほとんど人が使えていないのではないでしょう。
「英語は難しい」
と思うことは多々ありますが、
実は日本語も難しいのではないかと思うことがあります。
日本語は、ひらがな、カタカナ、漢字の三種類の文字を使い分けています。
外国人にとってはこれが難しいそうです。
まず、日本語の文字体系の複雑さが挙げられます。
ひらがなは日常の文章に欠かせませんが、カタカナは外来語や強調表現、擬音語などに使われ、漢字は意味を持つが読み方が複雑です。
例えば、「生」という漢字は、「生まれる」「学生」「一生」「生きる」など、文脈によって異なる読み方をします。
このため、日本語を学ぶ外国人はもちろん、日本人でも誤読することがあります。
さらに、同音異義語も多く、「橋」と「箸」など、会話では区別がつきにくいです。
次に、敬語の難しさがあります。
尊敬語、謙譲語、丁寧語を適切に使い分けることは、日本人でも難しいです。
「社長がいらっしゃる」と「社長がお見えになる」はどちらも尊敬語ですが、場面によって使い分ける必要があります。
特にビジネスシーンでは、間違った敬語を使うと失礼に当たります。
また、日本語の特徴として、曖昧な表現が多いことも難しさの一因です。
「ちょっと考えます」という言葉は、「前向きに検討する」という意味にも、「やんわりと断る」という意味にもなります。
この曖昧さは、文脈や相手との関係性を理解しなければ正しく解釈できません。
さらに、時代の変化によって新しい言葉が生まれたり、地域によって言葉の使い方が異なったりする点も、日本語を難しくしていえます。
例えば、「エモい」という言葉は若者の間ではよく使われますが、高齢者には馴染みが薄いです。
このように、日本語は生きた言語であり、常に変化し続けています。
ひらがな、カタカナ、漢字の使い分けに加え、敬語や曖昧な表現、言葉の変化など、日本語には難しい点が多いですが、奥深く、豊かな表現が可能になる言語であると思います。
日本語の難しさを楽しみながら学ぶことで、その魅力をより深く理解できるのかもしれません。
「こんなに難しい言語を扱っているのに、なぜ英語は覚えられない」
と思う人は多いと思います。
それにはそれなりの理由がありますが、またの機会に調べてコラムにしたいと思います。