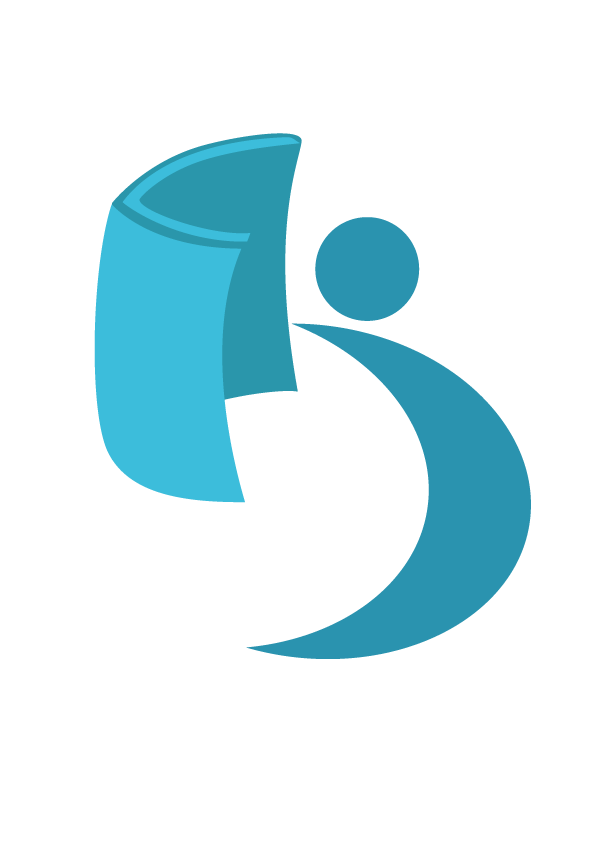私が勉強している中小企業診断士の試験科目でも出てくる経済学。
中小企業診断士試験だけではなく、公認会計士、国家総合職、地方上級、市役所など幅広い試験の科目としても出てきます。
経済学は学生時代に学んだことがある人は多いと思いますが、実際試験以外に使うことってあるのでしょうか。
今回は、経済学について簡単にまとめてみました。
経済学とは、私たちが日常で行う「お金の使い方」や「モノやサービスの生産と消費」を分析し、社会全体の仕組みを考える学問です。
経済学の目的は、限られた資源を効率的に使いながら、人々がより豊かに暮らせるようにすることにあります。
経済学には、大きく分けて「ミクロ経済学」と「マクロ経済学」の2つの分野があります。
ミクロ経済学は、個人や企業がどのように意思決定を行い、市場がどのように機能するかを研究します。
例えば、「価格が上がると消費者はどれくらい買う量を減らすのか?」や「企業はどのように価格を決めるのか?」といったことがテーマになります。
一方で、マクロ経済学は、国全体の経済活動を分析します。
GDP(国内総生産)、インフレ率、失業率などの指標を使い、景気の動向を理解し、政府の経済政策がどのような影響を与えるかを研究します。
経済学にはさまざまな基本原則がありますが、代表的なものとして、需要と供給の法則、機会費用の概念、インセンティブ(動機付け)が挙げられます。
需要と供給の法則では、価格は需要(買いたい人の数)と供給(売りたい人の数)のバランスによって決まります。
需要が多く供給が少ないと価格は上がり、逆に供給が多く需要が少ないと価格は下がります。
機会費用の概念では、何かを選ぶときには、他の選択肢を諦めることになります。
例えば、大学に通うことで得られる知識の価値と、働いて得られる収入のどちらが大きいかを考えるのが機会費用の考え方です。
インセンティブとは、人が利益を最大化しようと行動することを意味します。
例えば、税金を減らす政策をとれば、人々は働く意欲を高める可能性があります。
経済学は、日常生活やビジネス、政府の政策決定に広く応用されます。
企業が価格を設定するときには、消費者の行動を予測するミクロ経済学が役立ちます。
また、政府が景気を安定させるためには、財政政策や金融政策を適切に運用する必要があり、これはマクロ経済学の領域です。
経済学は、私たちの暮らしに密接に関わる学問です。
日常の買い物から国家の経済政策まで、幅広い場面で役立ちます。
経済の仕組みを理解することで、より賢い選択ができるようになり、豊かな生活を実現する手助けとなると思います。
簡単に説明すると上記の内容になりますが、実際の試験問題はもっと濃い内容であり、グラフや計算などとても難しい内容になっています。
経済学はとても奥が深い学問であるのです。